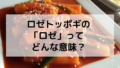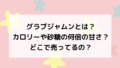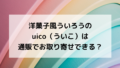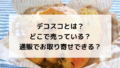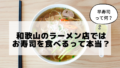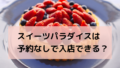普段何気なく言っている「ソーセージ」「ウインナー」「フランクフルト」。
スーパーでは同じ売り場に並んでいて、見た目も似ていますが、この違いって何でしょうか?
ハムやベーコンも形状は似ていますが、子どもに何が違うか聞かれてもちゃんと説明できる自信がありません。
そこで、ソーセージとウインナー、フランクフルト、ハム、ベーコンの違いをまとめてみましたので、参考にしてみてください。
ソーセージ・ウインナー・フランクフルトの違いは?

ソーセージとウインナー、フランクフルトの違いは、ひき肉を詰める腸の種類と太さによって分類されます。
それでは詳しくみていきましょう。
ソーセージとは?
「ソーセージ」は塩やハーブで味付けしたひき肉をケーシングに詰めた食肉加工品の総称です。
ケーシングとはソーセージを包む薄い膜のこと。
羊・豚・牛の動物の腸を使用していたり、人工のものを使用しているものもあります。
ひき肉には牛や豚、鶏などが使われており、原材料や製法によっていろいろな種類のソーセージが存在することになりますね。
世界には1000以上のソーセージが存在するといわれています。
そして、そのたくさんあるソーセージの種類のひとつに「ウインナー」が存在するんですね。
ウインナーとは?
「ウインナー」の正式名称は「ウインナーソーセージ」です。
オーストリアの首都ウイーンを発祥とするため、ウインナーソーセージの名が付きました。
日本のJAS規格によると、
【ウインナー】
・太さが20mm未満のもの
・羊の腸に詰めたもの
がウインナーソーセージであるとされています。
ウインナー以外にも規格で決められたソーセージがあります。
【フランクフルトソーセージ】
・太さが20mm~36mm未満
・豚の腸に詰めたもの
【ボロニアソーセージ】
・太さが36mm以上
・牛の腸に詰めたもの
これらはJAS規格によって定められたものなので、あくまで日本での分類となります。
「皮あり」「皮なし」ソーセージの違い
皮ありソーセージはケーシングに詰めたソーセージのことです。
皮ごと食べることができ、焼くと皮がパリッ、中がプリっとしておいしいですよね。
皮なしソーセージは食べることができないケーシングに詰めて作った後に、ケーシングを取り除いています。
皮がないので柔らかく、小さなお子さんでも食べやすいです。
冷めてもおいしく食べられるので、お弁当にも向いていますよ。
☆ウインナーソーセージ1kg【楽天市場】

ハムとは?
「ハム」は豚のもも肉を塊のまま塩漬けした食品になります。
塩漬けして熟成させた後は燻製やボイルをするものもあれば、加熱処理をしないものもあります。
日本では豚のもも肉以外の部位であっても、大きな形のまま加工したものをハムと呼んでいます。
・豚もも肉を使用した「ボンレスハム」
・豚ロース肉を使用したものを「ロースハム」
・豚肩肉を使用した「ショルダーハム」
・骨付きの豚もも肉を使用した「骨付きハム」
・加熱処理をしない「生ハム」
使用する部位によって名前が変わるということですね。
スーパーでよく見かける薄切りでパックされているロースハムは日本生まれなんだそう。
日本人には馴染み深いハムですよね。
ソーセージとハムの違いは、ソーセージはひき肉を詰めたものであるのに対し、ハムは豚のブロック肉を塩漬けしてから燻煙やボイルをしたものであることです。
☆北海道トンデンファーム DLG受賞セット【楽天市場】

ベーコンとは?
「ベーコン」は豚のバラ肉を塩漬けにして燻製したものになります。
バラ肉を使っているから焼くと脂が出てくるんですね。
豚バラ肉以外にも使用する部位によって呼び名が変わってきます。
・豚ロース肉を使用したものを「ロースベーコン(カナディアンベーコン)」
・豚肩肉を使用した「ショルダーベーコン」
薄切りタイプのものはいろいろな料理に使いやすく、ブロックタイプは厚切りにして焼いて食べてもいいし、好みのサイズにカットしてスープや炒飯の具としても使えますね。
まとめ
ソーセージにはいろいろな種類があり、ウインナーはソーセージの中の1つだったんですね。
スーパーで売っているソーセージも商品ごとに味や食感、香りなどがそれぞれ違うので、こんなにも違うのものかと感心してしまいます。
いろいろと食べ比べてお気に入りのソーセージを見つけるのもおもしろそうですね。