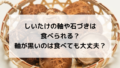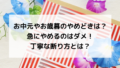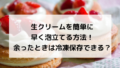銀杏(ぎんなん)は秋の味覚として親しまれている食材で、茶碗蒸しや炒め物、おつまみなど幅広い料理に活用されています。
しかし、調理の際に破裂してしまう危険があることをご存じでしょうか?
そこで活躍するのが「茶封筒」です。
「なぜ銀杏を茶封筒に入れるのか?」と疑問に思ったことがある方も多いはず。
本記事では、銀杏を安全に、そして美味しく楽しむために、茶封筒を使う理由や電子レンジでの調理方法、保存のコツを解説します。
銀杏を茶封筒に入れる理由とは?

茶封筒を使うメリットとは?
銀杏を加熱するときに茶封筒を使用することには、大きな意味があります。
まず第一に、銀杏は内部に水分を多く含んでいるため、急激に加熱すると内部の水分が膨張して殻が破裂しやすくなります。
これを防ぐために、茶封筒という通気性のある素材を使うことで、内部の蒸気を適度に逃がしつつ、加熱の圧力を緩和することができるのです。
さらに、茶封筒は紙製でありながら比較的耐熱性に優れており、電子レンジでの加熱にも安全に使用できます。
ビニール袋やラップと違い、熱によって溶け出す心配もありません。
また、使い捨てできるので衛生的で手軽な点も大きな利点です。
電子レンジでの加熱方法の注意点
電子レンジで銀杏を加熱する際は、まず銀杏を10〜15粒程度茶封筒に入れ、封筒の口を軽く二つ折りにして閉じます。
密閉しすぎると逆に圧力がかかりやすくなるため、空気が逃げる余裕を残しておくのがポイント。
その後、500〜600Wの電子レンジで30〜40秒ずつ様子を見ながら加熱します。
加熱中には「パンッ」という破裂音がすることがありますが、それが殻が割れて中身が加熱された合図です。
音がしたらすぐに取り出すようにし、過加熱は焦げや破裂事故の原因になります。
加熱時間を少しずつ調整することで、安全かつ美味しく仕上がります。
銀杏に含まれる成分とその魅力
銀杏(ぎんなん)は、イチョウの木になる種子で、秋になると独特の香りと共に道端で見かけることが多くなります。
その独特の香りは好き嫌いが分かれるところですが、食材として調理すると香ばしく、ほろ苦さの中にほのかな甘味を感じられる味わい深い一品になります。
銀杏にはデンプン質が豊富に含まれており、それによってホクホクとした食感が生まれます。
また、ビタミンB群、カリウム、鉄分、葉酸といった栄養素も含まれており、滋養強壮や疲労回復に役立つとされています。
銀杏の保存方法とそのコツ

冷凍保存の手順と目安
銀杏は鮮度が落ちやすいため、長期保存するなら冷凍が最適です。
購入後、殻付きのまま銀杏を洗って汚れを落とし、よく乾かしてからジップロックなどの密封袋に入れて冷凍庫で保存します。
この方法であれば2か月程度の保存が可能で、使いたい時に取り出してそのまま調理することができます。
殻をむいてから冷凍することも可能ですが、その場合は酸化しやすくなってしまいます。
ラップで小分けに包んでから保存袋に入れるなど、空気に触れないよう工夫すると風味が長持ちします。
冷凍しても銀杏特有のホクホク感は損なわれにくく、美味しく調理できます。
茶封筒やフライパンでの調理法
茶封筒を使った加熱方法のほかに、昔ながらのフライパンを使って殻付き銀杏を炒る方法も人気です。
フライパンに銀杏を重ならないように並べ、弱火〜中火でじっくりと炒ると、殻が徐々に割れ、香ばしい香りが立ち込めてきます。
ときどきフライパンを揺すりながら均等に火が通るようにすると、ムラなく美味しく仕上がります。
調理中に銀杏が破裂することがあるため、ふた付きのフライパンや深めの鍋を使うと安心です。
炒った銀杏はそのまま食べるだけでなく、塩をふっておつまみにしたり、料理の具材としても活用できます。
安全に楽しむための注意点
銀杏にはメチルピリドキシンという成分が含まれており、これが中毒の原因となることがあります。
特に子どもや高齢者は代謝が遅いため、摂取量に注意が必要です。
・大人の場合でも1日10粒程度
・子どもは3〜5粒まで
・5歳未満の子どもには食べさせない
これ以上食べると、嘔吐や痙攣などの中毒症状を引き起こす可能性があります。
加熱不足の銀杏は毒性が残りやすいため、しっかりと加熱することが大切です。
また、体質によっては少量でもアレルギー反応が出ることがあるため、初めて食べる際には少量から試して様子を見るようにしましょう。
銀杏の下処理と料理レシピ

銀杏の薄皮の取り方
銀杏の殻を割って中身を取り出すと、薄い茶色の皮がついています。
この薄皮はそのままでも食べられますが、口当たりが悪いため、多くの場合は取り除きます。
薄皮は熱湯に数秒くぐらせることで柔らかくなり、手やキッチンペーパーでこするようにすると簡単に剥けます。
また、茶封筒やフライパンで加熱した後であれば、皮が自然に浮いてくることもあるため、調理の流れで処理できることもあります。
皮を取り除くことで色も鮮やかになり、料理に使った際の見た目も美しくなります。
人気のおつまみレシピ
銀杏は素材そのものの味が引き立つ食材です。
最もシンプルな食べ方は、塩をまぶしてそのままいただく方法。
加熱して塩をふるだけで、抜群のおつまみになります。
他にも、ベーコンと一緒に炒めて香ばしさと旨味をプラスしたり、ニンニクやオリーブオイルでアヒージョ風にアレンジするのもおすすめ。
シンプルながらも奥深い味わいを楽しめます。
茶碗蒸しやトースターでの調理法
銀杏といえば、やはり茶碗蒸しが定番。
なめらかな卵液の中に銀杏が入ることで、ほんのりとした苦味とホクホクとした食感がアクセントになります。
また、殻を割った銀杏をアルミホイルに並べて、トースターで3〜5分焼くだけでも手軽に香ばしい一品が完成します。
☆茶碗蒸しの素【楽天市場】

銀杏の食べ方とおすすめの食材

食べ過ぎに注意!適切な量とは?
前述の通り、銀杏は美味しい食材でありながら、適量を守ることが大切です。
メチルピリドキシンによる中毒は、特に幼児に多く報告されており、症状としては嘔吐、けいれん、意識障害などが挙げられます。
大人でも一度に10粒以上の摂取は控えるよう心がけましょう。
習慣的に毎日食べるのではなく、週に1〜2回、料理に少量加える程度にとどめることで、安心して楽しめます。
適量を守ることで、健康的な食生活に銀杏を取り入れることができます。
子どもにも安心な料理法
子どもに銀杏を与える場合は、調理法と分量に特に気をつける必要があります。
加熱処理をしっかり行った上で、茶碗蒸しや混ぜご飯、おにぎりの具材として少量ずつ与えるとよいでしょう。
銀杏単体ではなく、他の食材と混ぜることで苦味が緩和され、子どもでも食べやすくなります。
銀杏が初めての場合は、1粒からスタートし、様子を見ながら量を調整しましょう。
体調に変化が見られた場合には、すぐに医療機関を受診することが大切です。
大人向け人気レシピ
大人向けには、銀杏の持つ独特の苦味や風味を活かしたレシピが人気です。
炊き込みご飯に加えると、秋の味覚を存分に楽しめる一品になりますし、銀杏の素揚げに塩をふっただけでも立派な前菜になります。
さらに、バター醤油で炒めたり、牛肉やキノコ類と一緒に炒め物にすることで、コクと香りが引き立ちます。
和食だけでなく、洋風のパスタや中華炒めなどにもアレンジしやすく、食卓のレパートリーを広げることができます。
銀杏を楽しむためのヒント

ギンナンを使ったアレンジ方法
銀杏は幅広い料理に応用できる万能食材です。
例えば、銀杏をペースト状にしてポタージュスープに加えれば、ほのかな苦味が大人の味わいを演出します。
パスタやリゾットのトッピングにすることで、見た目も華やかになり、食感のアクセントにもなります。
中華料理では、八宝菜や炒め物、春巻きの具材としても使われます。
銀杏を取り入れることで料理に季節感が生まれ、いつものメニューに変化を加えることができます。
爆発を防ぐための必須知識
銀杏の加熱中に起こる破裂事故は、加熱前の準備で防げることが多いです。
殻付きの銀杏に軽くヒビを入れておくことで、蒸気が逃げやすくなり、圧力の蓄積を抑えることができます。
また、加熱中に密閉しないよう心がけ、茶封筒や耐熱皿など通気性のある器具を使うことも重要です。
電子レンジでは加熱中に目を離さず、「パンッ」という音がしたらすぐに取り出すようにしましょう。
加熱時間を短めに設定し、様子を見ながら少しずつ延長することで、安全性が高まります。
まとめ
銀杏は秋の訪れを感じさせる日本の伝統的な食材のひとつです。
その美味しさと栄養を最大限に引き出すためには、加熱方法や保存、適切な食べ方を知っておくことが大切です。
茶封筒を使った加熱法は、銀杏を手軽に安全に楽しむための有効な手段であり、ぜひ活用していただきたい方法です。
これらの知識を取り入れて、旬の味覚・銀杏をより一層楽しんでください。