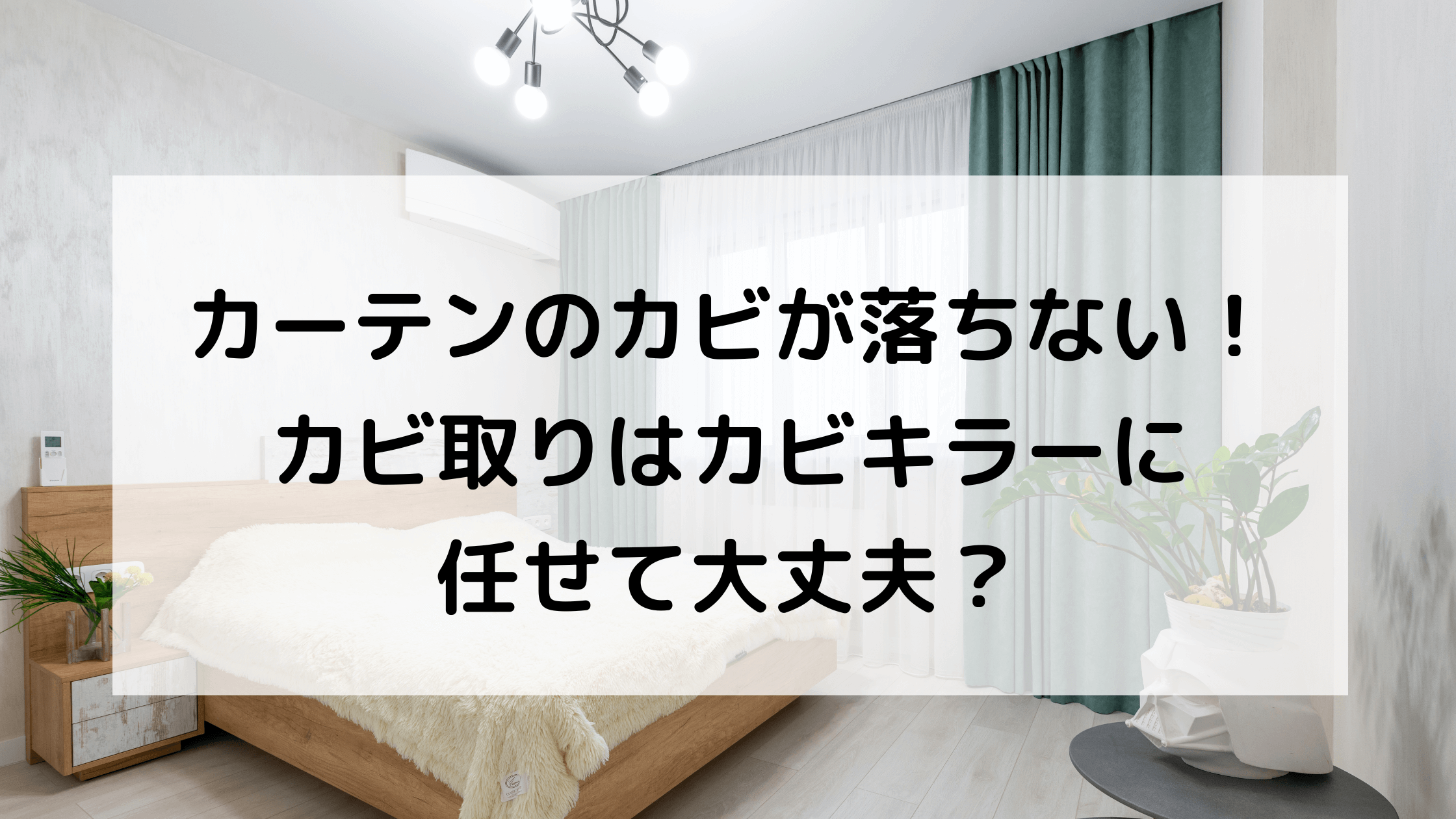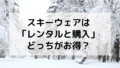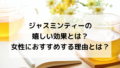連休にはいり、ずっと気になっていた所をやっとお掃除しました。
それがどこかと言いますと・・・カーテンのカビです!
レースカーテンについた黒い点々を確実に落としたいと思い、カビキラーを使ってみました。
果たしてカーテンのカビはカビキラーで落とせたのでしょうか。
また、カビキラー以外でのカビの落とし方やカビを生やさない予防方法についてもご紹介します。
カーテンのカビ落としにはカビキラーが効く!
家の北側の部屋につけているレースカーテンに黒い点々としたカビが発生していたので、カビキラーを使って落とせるか実際にやってみました。
なぜカビキラーで試したかと言いますと、
・前に塩素系漂白剤で試したときに完全に落ちなかった
・白いレースカーテンだったので多少の色むらや傷みは気にしないため
多少のリスクをおかしても完全に落としたかったのです。
まず、お風呂場にカーテンを広げて、カビの部分にカビキラーをシュッシュッと吹きかけます。
そして、しばらく放置。
その後、シャワーでよく流してから、洗濯機で洗います。
脱水後はすぐにカーテンレールにつけて乾かしました。


所々にあった黒い点々のカビがきれいに落ちました!
カビキラーで落としたら、カビがきれいに消えて晴々とした気持ちになりましたよ。
カーテンの色むらや傷み、臭いも特に気にならず、仕上がりに満足しています。
カビキラーを使う時の注意点
カーテンのカビ落としにカビキラーを使うときは、次のことに注意して行ってくださいね。
カーテンによってはカビキラーは強力すぎて脱色や傷む原因になってしまうため、誰にでもおすすめできるものではありません。
生地を傷ませずにカビを落としたい場合は、次にご紹介する方法を試してくださいね。
カーテンのカビの落とし方

カーテンのカビを落とすときはいきなり洗うのではなく、次のことを確認しておきましょう。
洗濯表示を見て、水洗いOKか確認しましょう。
水洗いができないカーテンは、クリーニング店で相談した方がいいかもしれません。
色落ちの確認方法は、白いタオルに液体洗剤を含ませて目立たない部分を軽くたたきます。
タオルにカーテンの色がつかなければOKですよ。
酸素系漂白剤を使う
酸素系漂白剤は色落ちしにくく、生地が傷みにくいのがメリットです。
酸素系漂白剤には、ワイドハイターやオキシクリーンなどがありますね。
【洗濯手順】
①大きなバケツにお湯と酸素系漂白剤を入れてよく混ぜる。
水よりお湯の方が落ちやすいです。
ただし、温度が高すぎると傷みの原因になりますので、ぬるま湯にしましょう。
②カーテンをしばらくつけ置きにして、やさしくもみ洗いやブラシで軽くこする。
③カーテンを畳んで洗濯ネットに入れたら、洗濯機で洗濯洗剤を使いいつも通りに洗濯をする。
洗濯ネットに入れるときは、プリーツに合わせてジグザグとじゃばら状に折ると乾いたときにきれいに仕上がります。
④カーテンレールに干す。
洗濯後はすぐにカーテンレールに吊るして乾かしましょう。しばらく放置しているとシワがついてしまします。
天気のいい晴れた日行う、窓を開ける、除湿器を使うなど早く乾くように工夫してくださいね。
塩素系漂白剤を使う
酸素系漂白剤で落ちないカビは、より漂白力の高い塩素系漂白剤を使いましょう。
塩素系漂白剤には衣料用ハイターやブリーチなどがありますね。
基本的な流れは酸素系漂白剤での洗濯の仕方と同じですが、次の点に注意が必要です。
色柄ものは白くなってしまうのでダメですが、白いカーテンでも微妙に色がかわってしまう可能性があります。
どうしてもやりたい場合は、少量で薄めて、目立たない部分で試すことをおすすめします。
塩素系漂白剤は、酸性の洗剤や酸性タイプの製品(酢やクエン酸など)を一緒に混ぜると、有害な塩素ガスがでて大変危険ですので注意してください。
カーテンにカビが発生する原因
そもそも、なぜカーテンにカビができるのでしょう?
一番の原因は湿気です。
梅雨になるとジメジメして湿度が高くなり、カビが生えやすいですよね。
また冬になると外と室内の温度差がでて、窓に結露ができます。
その水分がカーテンにつき、濡れた状態を放置しておくとカビが発生してしまいます。
カビが発生しないのが一番なのですが、普段カーテンを間近でじっくり見ることもないですし、あまり開閉しない窓だと結露の状態もよく確認しませんよね。
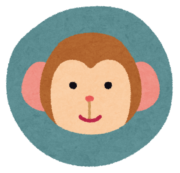
生えてしまったカビは仕方がない。どんどん広がる前に早めに落としましょう。
カーテンのカビを予防する方法

換気する
定期的に空気の入れ替えをして、カーテンまわりの空気が循環するようにしましょう。
1日数分程度でもOKです。
湿度が高いときは除湿機を併用するのも効果的です。
結露をとる
窓についた結露がカーテンに染み込む前に拭き取りましょう。
厚手のカーテンを閉めっぱなしにしていると結露に気付きにくいので、カーテンを開けて結露をチェックする習慣をつけるといいですね。
今は結露対策グッズもたくさん売っていますので、上手に活用しましょう。
定期的に洗濯をする
季節の変わり目や大掃除のときなど、年に1、2回洗濯をしましょう。
カーテンを外したときにカーテンレールや窓、サッシをアルコールを含んだウエットティッシュで掃除しておくといいですね。
まとめ
カーテンのカビは予防で防ぐのが一番ですが、発生してから気づくことも多いです。
早く気づけば落とせる可能性も高いですが、ひどくなるとホームクリーニングでは難しくなります。
カビを放置しておくとアレルギーの原因になったりもしますので、こまめなチェックと定期的な掃除で清潔な状態を保ちましょう。