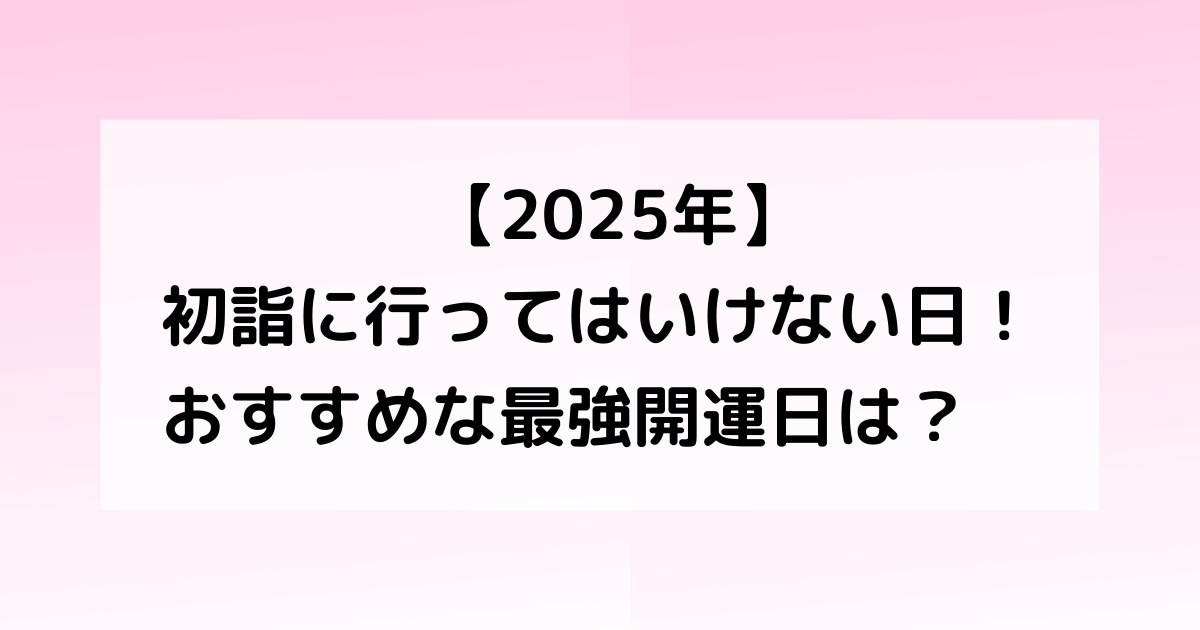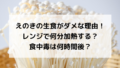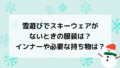お正月といえば初詣ですが、新しい1年の幸せを祈願しにいく人も多いことでしょう。
ただ、初詣はいつ行ってもよいわけではなく、避けたほうがよい日もあるのです。
そこで今回は、初詣に行ってはいけない日や時間帯について解説していきますよ。
また、2025年に初詣に行ったほうがよい最強の開運日についてもご紹介します!
【2025年】初詣に行ってはいけない日

初詣に行ってはいけない日には、忌中や不成就日、受死日があります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
忌中
忌中の間は、神社への参拝は避けましょう。
忌中とは、親族を亡くし「四十九日までの喪に服す期間」のことです。
故人の来世での行く先が未定であり、四十九日中は故人がまだ近くにいると考えられています。
そのため、四十九日が経過していない期間、初詣など神様の近くに行くことは避けるべきなんですよ。
なお、「喪中」の場合は、故人が亡くなってから四十九日が経過していれば、喪中でも初詣に行くことは問題ありません。
喪中とは遺族や親族が故人を偲び、喪に服する期間で、一周忌法要が終わるまでとされています。
不成就日
不成就日とは、十干十二支に基づいて特定される凶日のことを指します。
「不成就日に始めたことは、すべて成就しない」という縁起が悪い日とされています。
この日に神様にお願いごとをしても、願いがかなう可能性は低いため、初詣に適していないとされています。
不成就日は月に複数回発生しますが、2025年1月の不成就日は次の通りです。
【2025年1月の不成就日】
・1月5日(日)
・1月13日(月)
・1月21日(火)
・1月31日(金)
受死日
受死日は、暦の中でも縁起が悪いとされる大凶日です。
吉日と重なった場合、吉日のパワーを消してしまうほど悪い運気とされています。
そのため、この日に取り組んだことは何をやっても成就しないと言われています。
葬式以外は凶で、万事よくない日なので、初詣も避けた方がよいでしょう。
2025年1月の受死日は次の通りです。
【2025年1月の受死日】
・1月16日(木)
・1月28日(火)
初詣で避けたほうがよい時間は?
初詣は、なるべく日中に参拝するのがおすすめです。
夕方以降は陰の気が高まり、邪気がたまりやすくなるため、暗い時間に神社を訪れることは、神様に対する失礼な行為とされています。
また、暗い時間ですと周りがよく見えなかったり、神社によっては閉門するところもあるので、落ち着いて参拝することができません。
逆に午前中の参拝は、神社の空気も澄んでおり良い気を受けることができますよ。
大晦日の深夜に年越しで初詣をする場合は問題ありませんので、それ以降はできるだけ日中に参拝するようにしましょう。
初詣に適した日は?

初詣はいつまでに行かなければいけないという決まりはありませんが、初詣に適した日は、
・三が日
・松の内期間
・旧正月
になります。詳しくみていきましょう。
三が日
新年最初の3日間である1月1日~3日の三が日は、多くの参拝客で賑わい、最もお正月気分を味わうことができます。
昔から初詣は早くに行った方がよいとされ、三が日に参拝する人も多いことでしょう。
元日の午前中は最も混雑する日でもあり、2日や3日は徐々に緩和されていくものの、お正月にお参りを済ませたい人でまだ混雑することでしょう。
混雑を避けたい場合は、4日以降に行くのがいいでしょう。
松の内期間
松の内とは、正月の松飾りを飾っておく期間になります。
関東は1月7日まで、関西は1月15日までとされる場合が多いです。
松の内は、年神様が滞在している期間になるので、新年の始まりを年神様と一緒に過ごしているという気持ちで参拝するといいですね。
4日以降の神社はそれほど混雑していないので、ゆっくりと参拝することができるでしょう。
旧正月や立春
初詣は、旧正月や立春にいくのもよいでしょう。
旧正月とは、旧暦のお正月のことになります。
新暦でいうと、1月末から2月初旬にあたり、その年によって日にちが異なります。
2025年の旧正月は、1月29日(水)
また、二十四節気において春の始まりとされる立春。
1年の始まりとされる日でもあるため、立春に参拝するのもよさそうですね。
2025年の立春は、2月3日(月)
【2025年】初詣でおすすめな日は?
2025年の初詣で縁起の良いおすすめな日は、1月1日です。
2025年の1月1日は、1年の始まりである元日に「神吉日」が重なった、とても運気がよい日になるんですよ。
神社への参拝や祭事を行う日に適しているので、初詣にいって日頃の感謝の気持ちを神様に伝えてきましょう。

1月1日以外にも、1月3日も神吉日良が重なる吉日ですよ。
1月3日…「三が日」と「神吉日」が重なる吉日
2025年の初詣は、三が日にいくと縁起がよさそうですね!
☆カット生ずわい蟹【楽天市場】

まとめ
初詣は、忌中や不成就日、受死日を避けて、なるべく縁起の良い日に行きたいものですね。
2025年の最も初詣に適している日は、1月1日。
新年によいスタートがきれるように、縁起がよい日を選んでお参りにいきましょう。